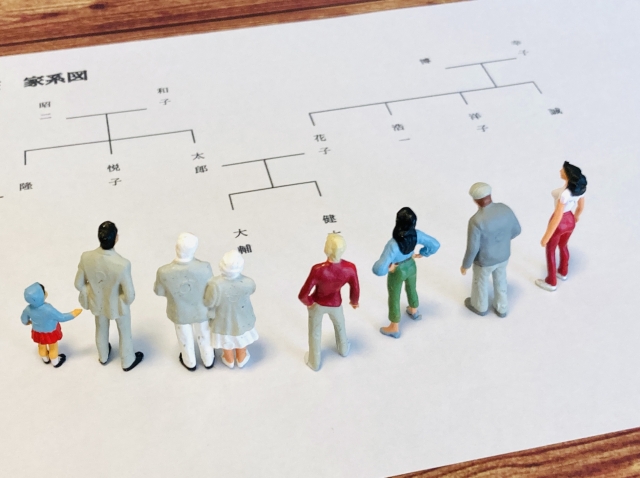コラム
家族信託と後見制度の比較 〜世田谷区の相続準備に最適な制度を選ぶために〜
- 2025.08.29
- カテゴリ:
不動産相続コラム
世田谷区は高齢化が進む地域であり、不動産資産を持つ高齢者も多く暮らしています。親が元気なうちは問題ありませんが、いざ認知症などで判断能力が低下すると、不動産の売却・賃貸・管理などができなくなり、相続準備や資産活用が一気に難しくなります。
そこで注目されているのが、「家族信託」 と 「成年後見制度」 です。どちらも本人に代わって財産管理を行う仕組みですが、その内容や柔軟性には大きな違いがあります。
今回は、世田谷区で不動産を持つ方に向けて、「家族信託」と「後見制度」の特徴を比較し、どちらを選ぶべきかのヒントを5つの視点から解説します。
第1部:家族信託と後見制度の基本的な違い
◆家族信託とは
・委託者(財産の所有者)が受託者(信頼できる家族)に財産の管理を任せる制度。
・公証役場で契約を結び、柔軟に設計できる。
・認知症リスクへの備えとして近年世田谷区でも注目度が高まっています。
◆後見制度とは
・判断能力が低下した本人に代わって、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理を行う制度。
・成年後見(判断力が失われた後に開始)と任意後見(元気なうちに契約)がある。
・公的制度として法的安定性が強い。
◆ポイント
家族信託は「予防型」であり、後見制度は「事後対応型」と言えます。
第2部:できること・できないことの違い
◆家族信託でできること
・不動産の売却や賃貸を子に任せられる。
・アパート収益を本人や家族の生活費に充てる。
・二次相続の受益者まで指定できる。
・世田谷区の空き家を売却して介護資金に充てることも可能。
◆家族信託でできないこと
・相続税の節税効果はない。
・債務整理や遺留分の侵害は不可。
◆後見制度でできること
・本人の生活費や医療費の支払い。
・不動産の管理や売却(裁判所の許可が必要)。
・悪徳商法などから本人を守る法的効力。
◆後見制度でできないこと
相続税対策や二次相続の指定など、柔軟な資産承継プランは作れない。
第3部:世田谷区における利用事例
◆家族信託の事例
・アパート経営者のケース
世田谷区でアパートを所有する80代男性が、認知症になる前に長男を受託者に指定。長男が賃貸経営を継続でき、収益を父の生活費に充当。
・空き家対策のケース
世田谷区の一戸建てを信託し、子が売却。介護施設の費用を捻出できた。
◆後見制度の事例
・認知症発症後のケース
世田谷区在住の女性が認知症を発症。家庭裁判所が後見人を選任し、銀行口座の管理を行った。ただし、不動産売却には裁判所の許可が必要で時間がかかった。
・家族が争っているケース
兄弟間で意見が割れ、第三者の弁護士が後見人に選ばれたことで公平性は保たれたが、費用が高額になった。
第4部:費用と手続きの違い
◆家族信託
・契約書作成費用:数十万円〜(公証役場手数料含む)。
・専門家への依頼費用:司法書士・弁護士で50〜100万円程度が目安。
・手続きは契約ベースなのでスピーディ。
◆後見制度
・裁判所への申立費用:数万円程度。
・後見人の報酬:月2〜5万円が継続的に発生。
・不動産売却などは裁判所の許可が必要で時間がかかる。
世田谷区の不動産を扱う場合、資産規模が大きいため「費用」よりも「スピードと柔軟性」が重要になる傾向があります。
第5部:選び方のポイントと併用の考え方
・家族信託が向いているケース
世田谷区に複数の不動産を持ち、将来的に売却や賃貸活用を予定している場合。認知症リスクを見据えて、柔軟に資産管理したい家庭。
・後見制度が向いているケース
すでに判断能力が低下しており、財産の保護を目的にする場合。相続人間で意見が合わない場合にも裁判所が関与する後見制度が有効。
・併用の考え方
家族信託で不動産の管理や承継を設計し、後見制度で日常の生活費や医療費管理を補うといった組み合わせも可能です。
世田谷区の不動産相続には「選択」と「準備」が必要
世田谷区の相続では、不動産が中心になるため「認知症になったときにどう管理するか」が非常に重要です。
・家族信託は柔軟で将来設計に強い。
・後見制度は法的安定性があり、すでに判断力が低下した場合に有効。
・世田谷区のように資産規模が大きい地域では、両者を比較し、必要に応じて併用することが安心につながる。
「どちらが正解か」ではなく、「自分の家庭に合う仕組みを早めに選ぶこと」が最大の相続対策です。
世田谷区に不動産を持つ方は、今から一度専門家に相談し、自分たちの家族に合った制度設計を始めてみてはいかがでしょうか。