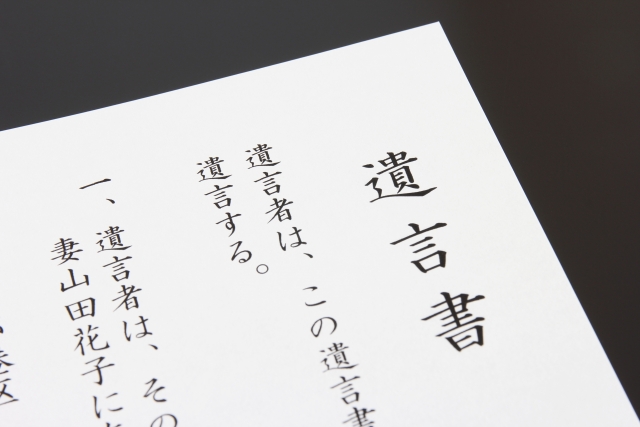コラム
自筆証書遺言の保管制度を活用するには 〜世田谷区で安心・確実な遺言を残すために〜
- 2025.07.22
- カテゴリ:
不動産相続コラム
「遺言書を書いたはずなのに見つからない」「内容をめぐって争いになった」――そんなトラブルは少なくありません。特に世田谷区のように高額な不動産を持つ家庭では、相続の影響が大きく、遺言書の不備が家族間の深刻な対立を招くケースもあります。
こうしたリスクを減らす制度として、いま注目されているのが「自筆証書遺言保管制度」です。この記事では、制度の概要から世田谷区での活用方法、注意点までを5部構成で詳しく解説します。
【第1部】自筆証書遺言とは?公正証書との違いも
まず、「自筆証書遺言」とは、全文・日付・氏名を自分で書き、押印した遺言書のことです。手軽に書ける一方で、以下のようなリスクもあります。
・紛失や改ざんの恐れ
・書式の不備で無効になるリスク
・保管場所を家族が知らず、見つけてもらえない
これに対して「公正証書遺言」は、公証人が関与するため形式的な不備が少なく、安全性が高い反面、費用や手間がかかります。
世田谷区でも近年、まず自筆で遺言を書いて保管制度を活用する方が増えています。
【第2部】法務局による自筆証書遺言保管制度とは
2020年からスタートしたこの制度は、法務局が自筆証書遺言を安全に保管する公的な仕組みです。
■ 制度の概要
・本人が法務局に出向いて、遺言書を提出
・遺言書の形式チェックを受け、問題なければ保管
・保管後は、相続人等が「遺言書情報証明書」の交付申請が可能
■ メリット
・紛失や改ざんのリスクがない
・家庭裁判所の検認が不要
・形式不備を防げる
・万一のときに、家族がスムーズに手続きを進めやすい
世田谷区民の場合、最寄りの東京法務局 世田谷出張所で対応可能です。
【第3部】世田谷区での活用事例と体験談
■ ケース1:80代女性が遺言をスムーズに残せた例
三軒茶屋に住む80代の女性が、相続人間のトラブルを避けるため自筆証書遺言を書き、法務局で保管。子ども2人に不動産をどう分けるかを明記し、後日相続が発生しても揉めることなく手続きが進行。
■ ケース2:検認不要で手続きがスムーズに
経堂の70代男性が残した遺言書が、世田谷法務局で保管されていたため、相続発生後すぐに遺言書情報証明書が発行され、家庭裁判所での手間を省くことができた。
このように、世田谷区のような都市部では、家族が離れて暮らしていることも多く、遺言書の所在が確実に把握できる仕組みが大変重宝されています。
【第4部】制度を活用するための手順と注意点
■ ステップ1:遺言書を自筆で作成
・日付・氏名・全文・押印を忘れずに
■ ステップ2:法務局へ予約を取り持参
・世田谷出張所(予約制)へ直接出向く
■ ステップ3:本人確認と形式チェックを受ける
・マイナンバーカード等の本人確認書類が必要
■ ステップ4:保管証明書の受領
・保管が完了すれば、証明書を受け取る
■ 注意点
・内容のチェック(文意や公平性)は行われない
・遺言の有効性は別問題(法律相談は専門家へ)
・財産状況の変化に応じて更新も考える
【第5部】活用前に確認すべきチェックリスト
・ 自筆で全文・日付・署名・押印を記入したか
⇒ 書式ミスは無効リスク
・ 財産と相続人の関係を整理したか
⇒ 誰に何を渡すか明確に
・ 法務局に予約をしたか
⇒ 予約なしでは対応不可
・ 本人確認書類を用意したか
⇒ マイナンバーカード・運転免許証など
・ 家族に制度の利用を伝えたか
⇒ 万一のときに発見されやすくするため
・ 更新や見直しのスケジュールを決めたか
⇒ 生活や財産の変化に応じて
遺言の「保管」で安心をカタチに
相続で一番多いトラブルは「意思がわからない」「話し合いがまとまらない」というものです。
世田谷区のように資産価値が高い地域では、その影響がとくに大きくなります。
だからこそ、遺言書を書くだけでなく、確実に残す仕組み=自筆証書遺言保管制度の活用が大切です。
費用も低く、手続きも比較的簡単なこの制度を、あなたの“将来の備え”としてぜひ検討してみてください。