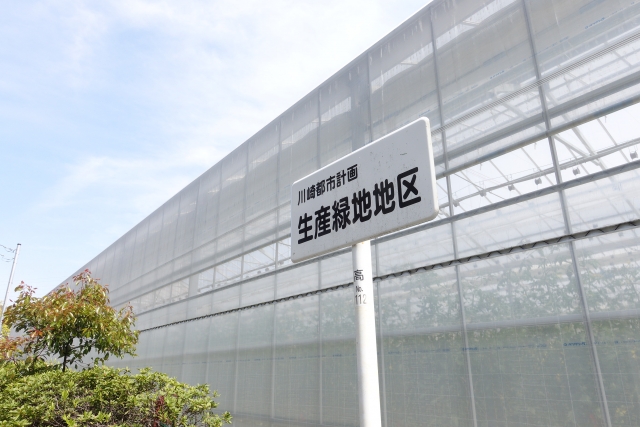コラム
世田谷区での生産緑地の相続について 〜都市農業と資産承継のバランスをどう取るか〜
- 2025.09.10
- カテゴリ:
不動産相続コラム
世田谷区は東京都内でも屈指の住宅地ですが、その一方で農地が点在しているのも特徴です。等々力、砧、喜多見、成城などには都市農業を支える農地が残り、その多くが「生産緑地」に指定されています。
生産緑地は、農業を一定期間継続することを条件に税制優遇を受けられる仕組みであり、都市部の農業を守るために制度化されました。世田谷区で生産緑地を相続する場合、宅地やアパートと違い「すぐに売る」「自由に転用する」とはいきません。農業の継続か、将来の活用計画かを家族で慎重に検討する必要があります。
本記事では、世田谷区で生産緑地を相続する際の手続きや注意点を5つの観点から整理し、相続における実務対応を分かりやすく解説します。
生産緑地とは何か?世田谷区における基礎知識
・生産緑地地区の指定
市街化区域内の農地で、一定規模以上かつ農業継続が可能な土地が指定されます。世田谷区では特に砧や喜多見で多く指定されています。
・主な効果
固定資産税が宅地並みに高額になるのを防ぐため、農地としての課税が維持される。相続税についても「農地の納税猶予制度」が適用されやすくなる。
・30年ルール
生産緑地は原則30年間農地として維持する義務があります。指定から30年経過すると「特定生産緑地」として更新されるかどうかを選択できます。
世田谷区における相続では「農業を続ける意思があるか」が最大の分かれ道です。
世田谷区で生産緑地を相続した場合の手続き
1.相続登記
生産緑地も不動産ですから、相続人への登記は必須です。義務化されたため放置できません。
2.農業委員会への届出
相続によって所有者が変わった場合、世田谷区役所の農業委員会へ届出が必要です。
3.農業継続の意思確認
相続人の中で誰が農業を継ぐのか、あるいは継がないのかを決定します。
4.納税猶予制度の申請
農業を継続する場合、相続税の納税猶予を利用できる可能性があります。
生産緑地相続で起きやすいトラブル
・相続人間の意見対立
「農業を続けたい人」と「売却して現金化したい人」で揉める。
・納税資金の不足
農地評価が高いため相続税額が大きくなるが、現金化しにくく資金繰りに困る。
・宅地転用できない不便さ
生産緑地指定のため、すぐには宅地や駐車場にできない。
・手続き遅れによるペナルティ
農業委員会への届出や税務手続きを怠ると罰則の可能性も。
世田谷区の現場でも「父の農地を相続したがどうしていいか分からず放置した」という声が非常に多いです。
世田谷区で選べる対応策
1.農業を継続する
家族が農業を続けることで、税制優遇を受けながら土地を守ることが可能。
2.特定生産緑地の指定を受ける
30年経過時に「特定生産緑地」として再指定すれば、引き続き優遇を受けられる。
3.買取申出制度を利用する
農業継続が難しい場合、市町村に買い取りを申し出る。ただし、実際に買い取ってもらえるケースは限られるため、売却や活用までに時間がかかる。
4.市民農園や貸し農園として活用
農業を継がずとも貸し出すことで収益を得られる。世田谷区でも都市農業振興策として推進中。
生産緑地相続の実務チェックリスト
・ 相続登記を済ませたか
・ 世田谷区農業委員会に相続届を提出したか
・ 生産緑地の指定状況を確認したか
・ 相続人全員で農地の扱いを協議したか
・ 納税猶予制度を検討したか
・ 30年経過後の扱いを見据えて計画を立てたか
・ 市民農園・貸し農園など収益化策を調べたか
・ 専門家(司法書士・税理士・不動産会社)に相談したか
世田谷区の生産緑地相続は「放置せず計画的に」
世田谷区の生産緑地を相続する際は、宅地やアパート相続と比べて手続きが複雑で、自由度も限られます。
・農業委員会への届出を怠らない
・納税猶予制度を上手に使う
・家族で農業継続の意思を確認する
・将来の活用計画を立てる
生産緑地を「どう引き継ぐか」を放置してしまうと、税負担や家族間のトラブルが一気に表面化します。逆に、早い段階から計画を立てれば、世田谷区の農地を守りながら相続を円滑に進めることができます。